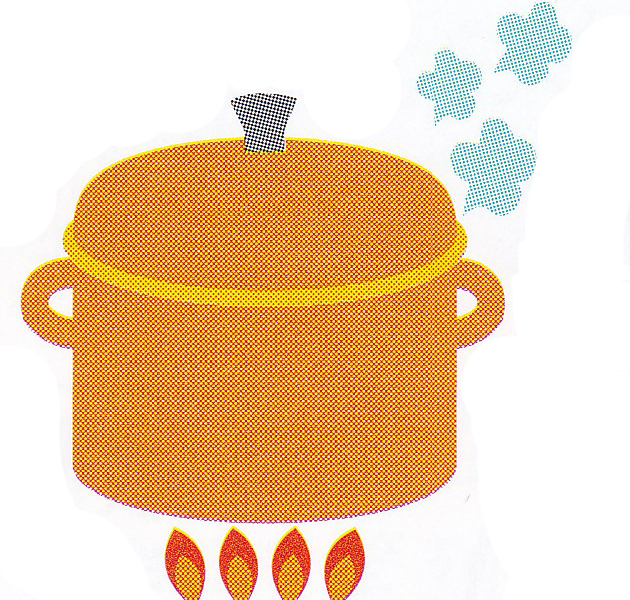食中毒に気をつけましょう

例年に比べると涼しいような気がしますが、季節はいよいよ夏。高温多湿の季節です。夏バテで身体の抵抗力も低下することもありますので、食中毒に気をつけましょう。
腐敗と食中毒は違う!?
見た目や臭いに変化がなくても、食中毒になり得ます。
食中毒の原因となる物質は、化学物質から自然毒まで多種多様ですが、主な原因は「細菌」と「ウィルス」です。
腐敗……微生物が増殖して、食品成分を分解。 ↓ 食品本来の味・香り・色が損なわれ、食べられなくなる。 (人間に有用な場合を「発酵」といいます。(例)納豆、酒、ヨーグルト等々)

食中毒…特定の微生物が食品中で増殖する。これを食べると食中毒になる。
(毒素を出す菌もいる)
※臭いや見ため、味にほとんど変化がない!
つまり、臭いや見た目に問題はなくても、食中毒になり得るのです!
大げさに言うと、腐敗が始まっていても、食中毒を起こす菌が増えていなければ、発生しないのです。(※だからと言って、食べないで下さいね。)
食品や手指に食中毒を起こす原因(菌やウィルス)がいないか、いても食中毒を起こす量まで増えていなければ、発生しません。(毒素を出す菌を除く) だからこそ、食中毒のことを知って、上手に対策して食事を楽しみましょう。
食品や手指に食中毒を起こす原因(菌やウィルス)がいないか、いても食中毒を起こす量まで増えていなければ、発生しません。(毒素を出す菌を除く) だからこそ、食中毒のことを知って、上手に対策して食事を楽しみましょう。
日本では約20種類の微生物が食中毒微生物として指定されています。①栄養 ②水分 ③温度 です。
食中毒予防には、この3つの条件を断ち切る事と、菌が増える時間を与えない事が重要になります。
食中毒予防の3原則 ~つけない、ふやさない、やっつける~
①つけない
食べ物を扱う前には、必ず石けんで手を洗いましょう。また、違う食材を扱う際にも必ず洗い直しましょう。調理器具も食材が変わるたびに洗い、殺菌することが理想的です。

②ふやさない
細菌の多くは、10℃以下で増殖がゆっくりとなり、-15℃以下で増殖が止まります。たとえ食中毒菌が食材にいたとしても、少量なら心配ありません。購入後の食材は、できるだけ早く冷蔵庫へ。でも過信は禁物です。早めに調理し、早めに食べましょう。
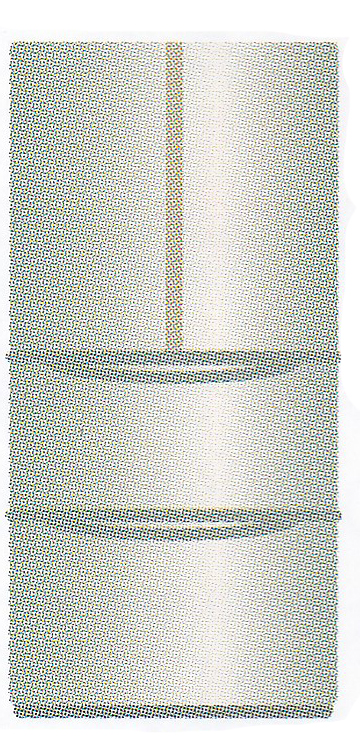
③やっつける ほとんどの細菌は加熱によって死滅します。特に肉料理は中心まで火を通しましょう。目安は中心部の温度が75℃で1分以上過熱することです。ふきんやまな板、調理器具も洗浄後は殺菌しましょう。